『季節_探訪・・時節感慨』
紅葉・黄葉の探索は、相模原公園で打ち止め。
例年のことだが、その理由は前回記した通り。
この相模原公園で最近知ったのが原種のシクラメン。
植栽されたものだろうが、なんとも可愛い花である。
このシクラメン、原種のCyclamen hederifoliumらしい。
塊茎(tuber)をもち、根は上と横から出て塊茎はかなり扁平。
ヘデリフォリウムの特徴、塊茎の大きさが幅24㎝に達する。
葉は、ハート形で先が尖る。hederifoliumの根は上と横から出る。
シクラメンhederifoliumは、最も普及しているシクラメン種だそうだ。
フランス南部からトルコ西部、地中海の島々の森林、岩場に自生。
ヘデリフォリウムはラテン語のヘデラ(アイビー)と葉に由来する。
葉は、通常は両側に2〜3個、ツタ(ヘデラ)の幼葉に似ている。
hederifoliumの葉柄と花の茎は外側に成長しつつ上に成長していく。
原種シクラメンの周囲は、ケヤキの高木が形よく生育している。
ドッグランもあったり子供が遊べる場所もあり落ち着いた雰囲気。
訪れると、ほっとする、心やすまる公園。
* * *
今年も後数時間でおわる。殺伐とした年だった。
きょうの昼間、東京の木場まででかけた。
年の瀬であっても何処か活気がなく寂しげに感じた。
来るベク新年では、良き社会に向かうよう祈り希する。
ブログるのみなさん、良い年をお迎えください。
本年は、お世話になりました。来年も宜しくお願いいたします。




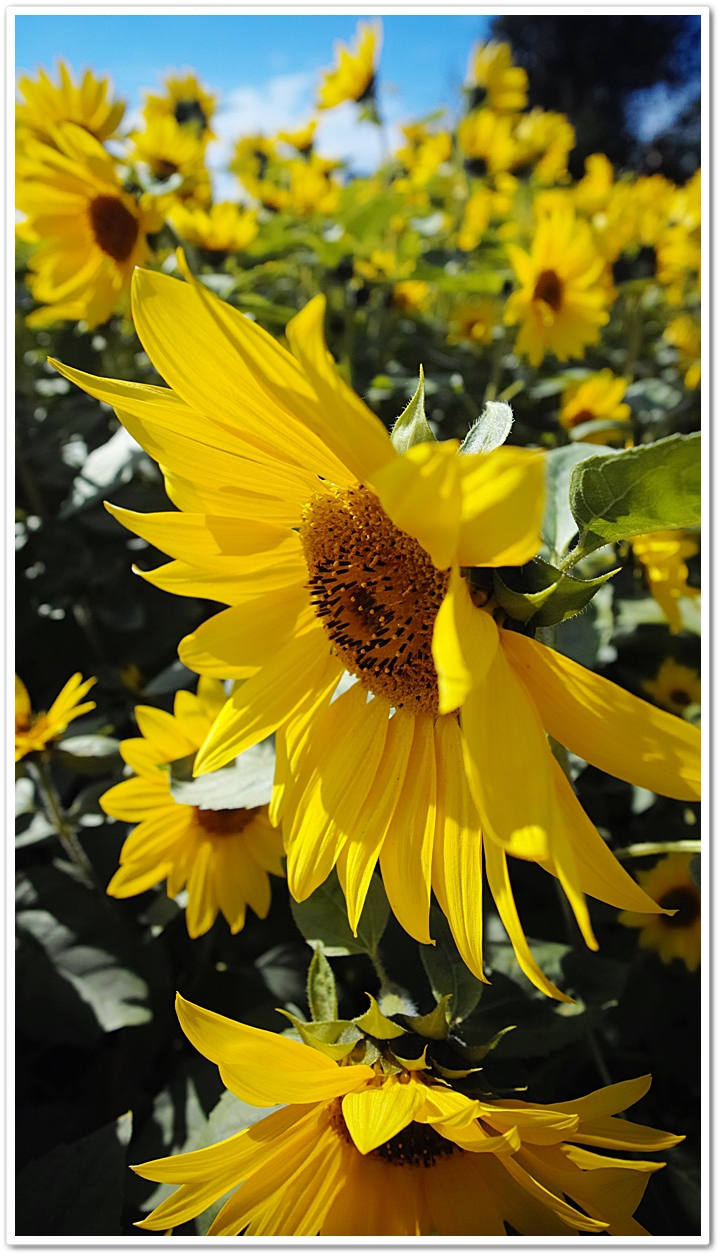



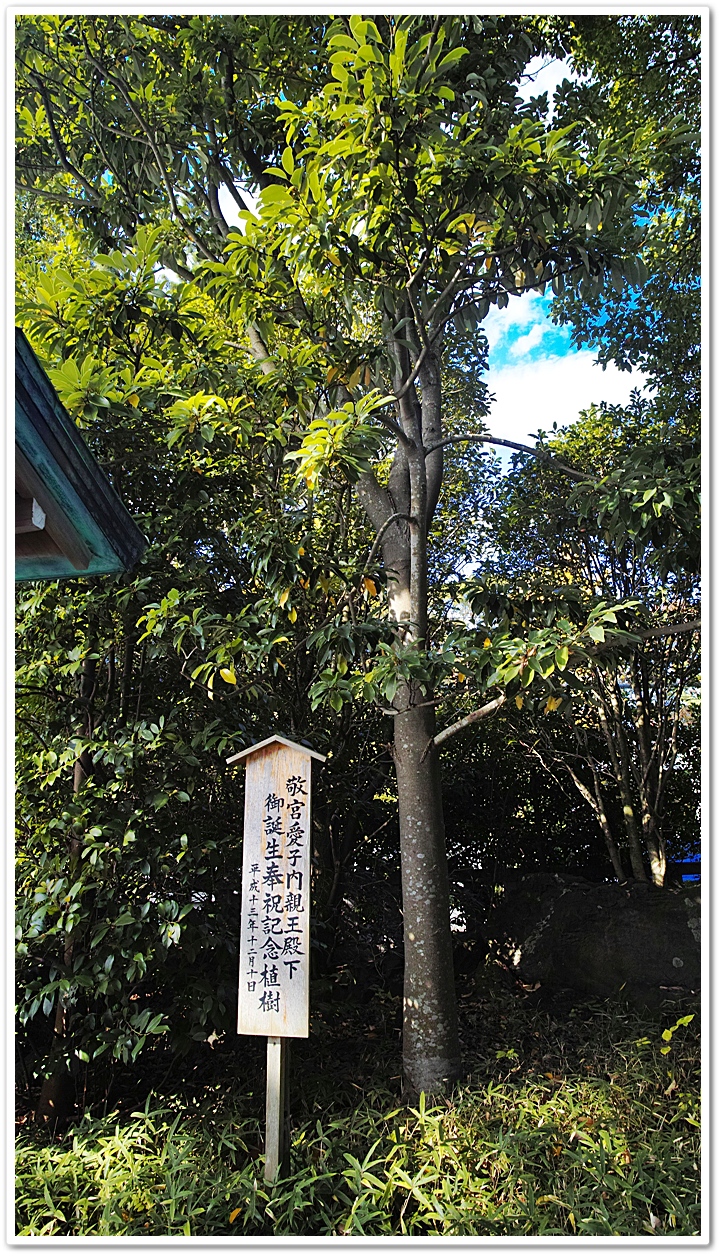
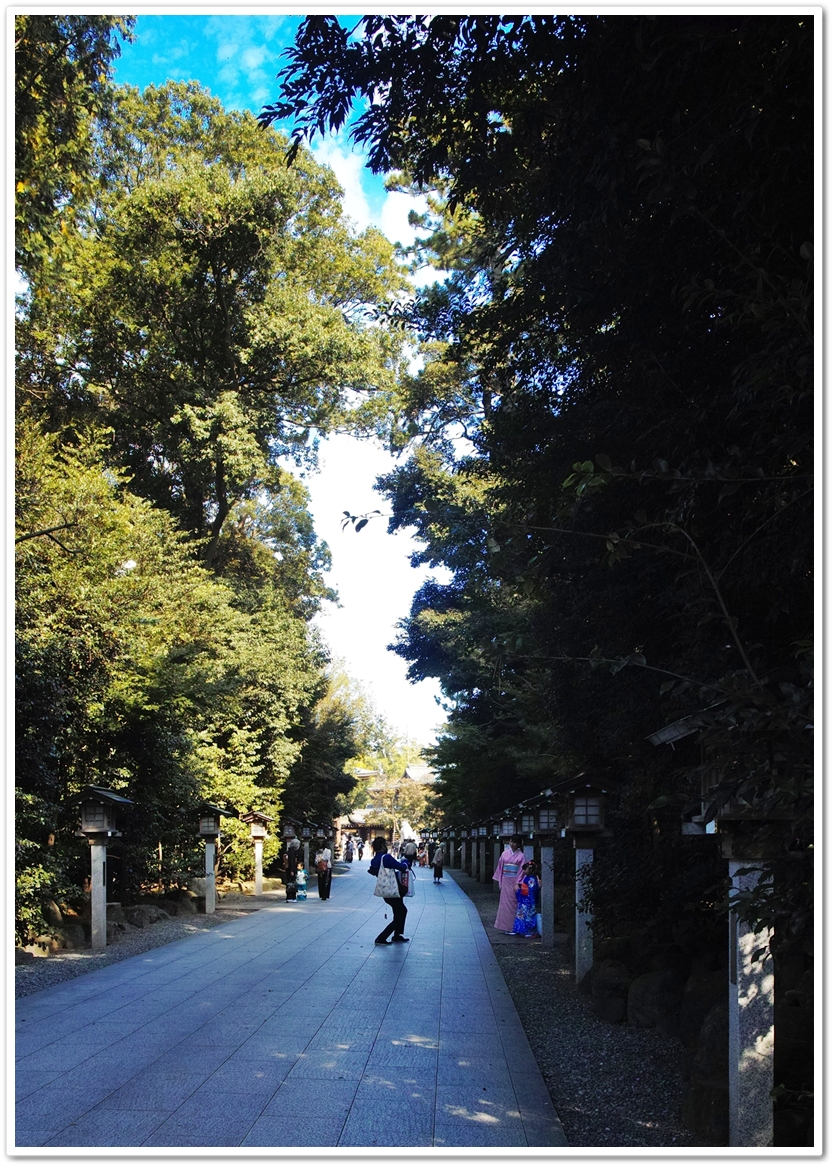








 プラン
プラン  dote
dote