《自宅近くの小公園・植栽された小さな花 ❖’23/6/8❖》
別名のようにキキョウ科だがホタルブクロ(カンパニュラ)属で桔梗の仲間ではない。
ホタルブクロ属の宿根草だが、丈夫で関東以北では野生化している所も確認されている。
原産地はヨーロッパ。カンパニュラの仲間は北半球を中心に約300種もある由。
日本には大正時代に渡来。強健性質でよく繁殖する。そして草丈は、150cmにもなる。
釣鐘状の花、青紫で旗竿の様に連なり10~20個下向きにつけ、花は3㎝程で5裂する。
§ § § § §
梅雨と言えば紫陽花が真っ先に思い浮かぶ。鎌倉も紫陽花一色だ。
観光地ゆえ仕方ないのだが、鎌倉の自然、道端の小さな花もおつなものだ。
僕の子供時代の鎌倉は、市の80%位が緑であった。
三方が緑、その中に市街地があり前は海。緑の要塞が、鎌倉の特徴だ。
半世紀前までは、鎌倉は緑濃い素朴なところだった。
今や高級住宅地である七里ガ浜の丘陵地帯は、雑木林であった。
海岸線の西側、稲村ケ崎までが住宅地(姥が谷が旧鎌倉の西の端)だった。
住所的に見ても僕の子供頃は稲村が崎と言う住所名ではなかった。
鎌倉市極楽寺字一の谷(いちのやと)・・・番地と言うのが番地名。
この一の谷のどんずまりに往古には、聖福寺があった由。
それ故、聖福寺谷とも呼ばれていた、と記録がある。
今の鎌倉山から稲村ケ崎海岸に小川が流れていた。
聖福寺跡辺りに小さな滝があり、那智の滝と呼んでいたと記憶する。
この辺り、海岸特性の野草がたくさん自生していた。
そんな花を観察に時折、両親に連れられて散策したものだ。
那智の滝近くには、ホタルブクロが自生していたと記憶する。
更にこの小川には、蛍もいた。今みれたらよかったのに。。!
今の七里ガ浜住宅地辺りでその昔、TV時代劇?”隠密剣士”のロケもやっていた。
蛍を見に行った時、注意されたのが蛇であった。
小川の脇の草むらに懐中電灯を照らす・・明かりが点滅しない、それは蛇の目!!
そんなことを教えられた。小さな地史、しっかりと語り継いでほしいものだ。
「令和伍年(皇紀2683年)6月10日、記」
別名のようにキキョウ科だがホタルブクロ(カンパニュラ)属で桔梗の仲間ではない。
ホタルブクロ属の宿根草だが、丈夫で関東以北では野生化している所も確認されている。
原産地はヨーロッパ。カンパニュラの仲間は北半球を中心に約300種もある由。
日本には大正時代に渡来。強健性質でよく繁殖する。そして草丈は、150cmにもなる。
釣鐘状の花、青紫で旗竿の様に連なり10~20個下向きにつけ、花は3㎝程で5裂する。
§ § § § §
梅雨と言えば紫陽花が真っ先に思い浮かぶ。鎌倉も紫陽花一色だ。
観光地ゆえ仕方ないのだが、鎌倉の自然、道端の小さな花もおつなものだ。
僕の子供時代の鎌倉は、市の80%位が緑であった。
三方が緑、その中に市街地があり前は海。緑の要塞が、鎌倉の特徴だ。
半世紀前までは、鎌倉は緑濃い素朴なところだった。
今や高級住宅地である七里ガ浜の丘陵地帯は、雑木林であった。
海岸線の西側、稲村ケ崎までが住宅地(姥が谷が旧鎌倉の西の端)だった。
住所的に見ても僕の子供頃は稲村が崎と言う住所名ではなかった。
鎌倉市極楽寺字一の谷(いちのやと)・・・番地と言うのが番地名。
この一の谷のどんずまりに往古には、聖福寺があった由。
それ故、聖福寺谷とも呼ばれていた、と記録がある。
今の鎌倉山から稲村ケ崎海岸に小川が流れていた。
聖福寺跡辺りに小さな滝があり、那智の滝と呼んでいたと記憶する。
この辺り、海岸特性の野草がたくさん自生していた。
そんな花を観察に時折、両親に連れられて散策したものだ。
那智の滝近くには、ホタルブクロが自生していたと記憶する。
更にこの小川には、蛍もいた。今みれたらよかったのに。。!
今の七里ガ浜住宅地辺りでその昔、TV時代劇?”隠密剣士”のロケもやっていた。
蛍を見に行った時、注意されたのが蛇であった。
小川の脇の草むらに懐中電灯を照らす・・明かりが点滅しない、それは蛇の目!!
そんなことを教えられた。小さな地史、しっかりと語り継いでほしいものだ。
「令和伍年(皇紀2683年)6月10日、記」









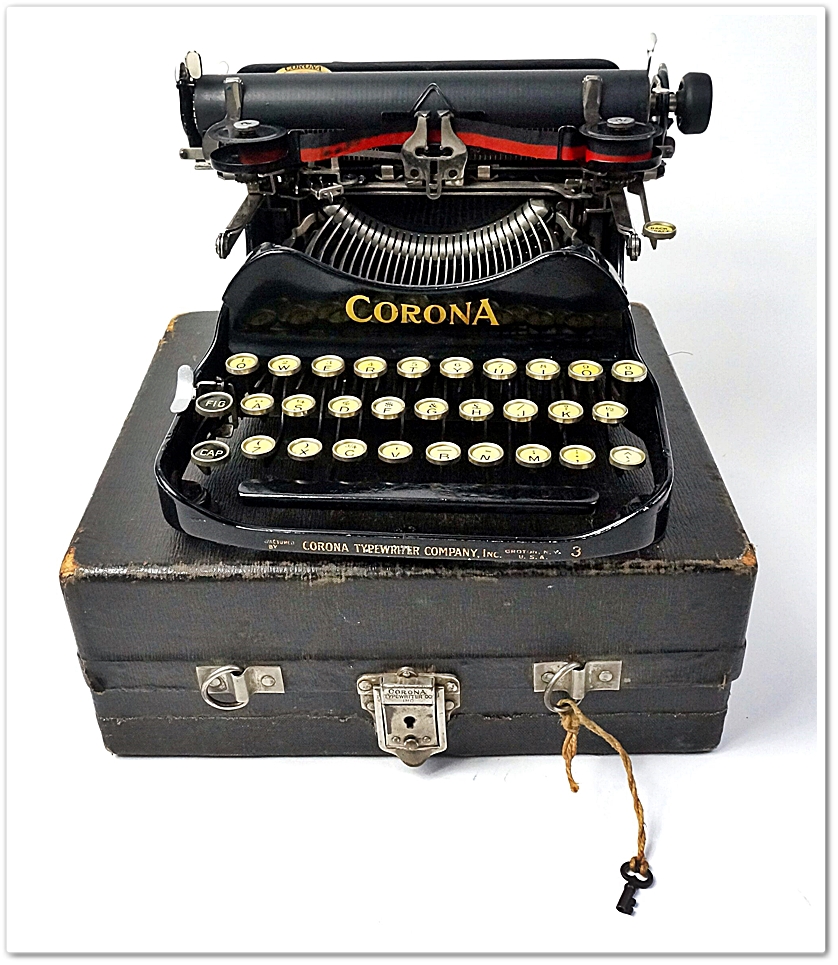
 くまごろう
くまごろう  dote
dote  プラン
プラン
No Latest Comments