柚子の実がまた少し大きくなった。10月8日のブログルには20ミリ位と書いたが、今日計ってみると31ミリだった。9月4日には12ミリだったから、ゆっくりながら少しづつ成長していることになる。昨年の10月23日には直径70ミリ位の黄色く色付いた実が2個なっていたのだから、それに比べると今年は大分遅い。
さくらが咲いた4月はじめに、それまで鉢植えで室内に置いていた柚子の木をフロントヤードに植えたが、その後当地は例年になく寒い春となり多くの葉が落ちでしまった。5月になって暖かい日が続いたが柚子の木は元気がなく、枯れてしまったかと心配したが、6月になってようやく新しい葉が生え始め、その後はすこやかに成長を続けてきた。
春先にマーサーアイランドの気候に慣れるために時間がかかったので、柚子の実の生育が遅いのはやむを得まい。このまま順調に育ち、来年1、2月の鍋料理がうまい季節までに50ミリ程度の青玉でよいから収穫出来れば上出来だ。

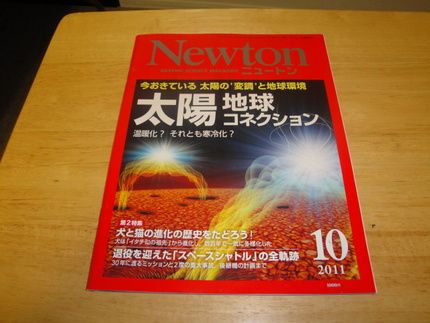
雑誌ニュートンの10月号をようやく手に入れた。本来なら10月初めにはシアトルの紀伊国屋で入手出来るのだが少し出遅れたために購入出来ず、10月号を日本から取り寄せてもらうはめとなった。紀伊国屋の話では毎月3冊しか入荷していないとのこと、これから確実に入手するために1年間の定期購読を申し込んだ。それにしてもニュートンのような科学雑誌が当地では3冊しか読まれていないとは、日本の科学離れが叫ばれてから久しいが、元科学少年のくまごろうにとっては寂しい限りである。
ニュートン10月号を是非読みたいと思ったのは、特集が『太陽・地球コネクション、温暖化?それとも寒冷化?』で、この科学雑誌は地球温暖化の問題をどのように取扱うのかに関心があったからである。
この特集では2004年より2010年の間で太陽に黒点のなかった日が836日におよび太陽の活動が弱まっていることから説き起こし、黒点が強力な磁石であること、太陽からは可視光線以外にも紫外線やX線などの電磁波が放射されており、それらの強さが黒点の活動と深く関わっていること、黒点活動が低下した1645年から1715年のマウンダー極小期には地球に冷害が襲ったこと、黒点がほとんどない時期である極小期から次の極小期までの太陽活動の周期が約11年であること、1755年から始まる第1周期から数えて第23周期に当る1996年からの周期は13年と異常に長かったことなどを多くのデータに基づいて解説している。マウンダー極小期の直前には2周期に渡りこの周期が13年だったこととあわせて考えるとやや不吉である。
太陽活動の変動による可視光線の変化は約0.1%であり、地球表面温度への影響は0.1℃程度でほとんど影響はないが、近紫外線は1-10%変化し、地球表面から50kmの高空の気温が1-2℃変動することがわかっている。しかしこの変動が地表に及ぼす影響は詳しくはわかっていない。
太陽活動が活発な時は太陽の強力な磁力が超新星爆発によって生じた陽子や電子などの粒子である銀河宇宙線の太陽系への侵入を防いでいるが、太陽活動極小期には太陽の発する磁力が弱くなり、地球に銀河宇宙線が侵入しやすくなるという。銀河宇宙線が多いと大気中の分子や原子をイオン化し、それらが水蒸気を集めて雲が発生しやすくなる、という説がある。この説によれば宇宙線が多いと雲の量が増えて太陽光がさえぎられ、地表温度が低下することになる。
2011年7月6日付くまごろうのひとりごとでは世の中が地球温暖化で騒いでいる一方、科学者による太陽活動の研究結果として地球寒冷化の可能性を述べたが、ニュートンではNASAや日本の太陽観測衛星による太陽の異変観測の重要性を説き、温暖化するのかあるいは寒冷化するのか結論付けてはいない。
20世紀に入ってからの人類による爆発的な化石燃料の使用は大量の二酸化炭素を発生させ、それが地球環境に悪影響を与えているかもしれない、という思いは大切であり、将来の化石燃料の消費を削減すべきだという考え方は正しいだろう。しかし現在の地球温暖化議論については、大気中の温暖化ガスとして水蒸気がその97%を占めているのであり、大気中に400ppmしか存在しない二酸化炭素の影響がどの程度であるか科学的にはまだはっきりしていない上、太陽活動や近赤外線による高空の温度変化の地表への影響や銀河宇宙線の影響など科学的データに基づく検討がまだまだ必要である。
科学的な知見に基づかない政治的なかけひきで地球温暖化を議論し、日本は2020年までに1990年比で二酸化炭素を25%削減する、と鳩山前総理が国連で宣言したのはあまりにも非科学的だと思う。


天気予報では週の初めから土曜日は雨とのこと、水曜日頃から今週の土曜定例ゴルフは雨と覚悟が出来ている。金曜日も雨、土曜日も明け方頃から雨足が強くなり、グリーンに水溜りが出来るようなら屋根付のクラブのドライビングレンジでショットの練習をすればよい、とレインパンツにレインジャケットを着用して雨の中クラブに向う。
クラブに到着する頃には霧雨状態、これならラウンド出来るかな、と思いつつウォームアップ開始。仲間も次々に到着して10時36分のティータイムまでショットやパットの練習。他のメンバーも続々とスタートするが、秋から冬に雨の多いシアトルでは天気予報を見てゴルフの計画を立てていてはラウンドする機会が激減する。雨が降れば傘をさしてラウンドすればよい、と割り切らねばならない。
いよいよティータイムになると一陣の風が吹き、まるでわれわれのスタートに合わせるように傘なしではいられないようなにわか雨が降出す。内心は嫌だなと思っていても、表向きは何のこれしき、と強がりを言いつつ1番ホールのティーグラウンドを後にする。
雨のために飛距離がのびないせいか2打目がグリーンに届かないでショートする。1番、3番、4番では雨に濡れて砂が重たくなったバンカーに入るが、このところバンカーショットには自信のあるくまごろうにとっては問題にならない。特に2番ホールではピンまでの距離がかなりあったので、重い砂でのブラストショットではなく、サンドウェッジのフェースでボールを直接打ち、ピンまで3ヤードくらいまで近づけることが出来た。
雨のゴルフは忙しい。ボールを打つ前に手やクラブのグリップをタオルでよく拭き、グリップが滑らないようにしなければならない。つくづく手があと2本あれば便利なのにと思う。おまけに芝生は濡れており、地面が水を含んでやわらかくなっているところもあるため足を取られやすく、歩を進めるのにいつもより力が要る。
5番ホールから雨が小降りとなり、7番ホール以後は傘をたたんでプレー出来るようになった。雨で濡れたグリーンはいつもより遅く、強めにパットしないとピンに届かないが、ピンより上につけると下り坂でのボールは意外と早く、パットのスピードコントロールが難しい。このような秋・冬グリーンに慣れればそれなりに対応出来るが、雨降りシーズン最初のラウンドでは3パットが多くなる。
上がってみれば48/47の95、満足出来るスコアではない。雨降りによるやわらかいフェアウェイでのダフリと少なくない3パットを反省。しかし今日はくたびれた。いつもの2倍歩いたような気がする。

ガラスと言えば簡単に割れるこわれものの代表のようなもので、最近ではあまり聞かないが、昭和の頃は少年たちが道路や狭い公園で野球をやってご近所の窓ガラスをよく壊したものだ。
ガラスは圧縮応力には比較的強いが引張り応力には弱く、例えば野球のボールがガラスに当った場合、ボールの当ったガラスの外側表面には圧縮応力がかかるので耐えられても、裏側表面にはたわみによる引張り応力がかかり、この応力が裏側表面にある目には見えない微細な傷に集中してガラスが裏側表面から破損する。この微細な傷は製造過程で溶融したガラスが他の物体と接触して生じるが、もしもガラス表面の微細な傷が皆無なら、ガラスの引張り強度は鉄よりも高いと言われている。
ペアガラスの窓では、外側のガラスにボールなどが当って破損する時、外側のガラスが飛来した物体の運動エネルギーを吸収するため、内側のガラスは割れないことが少なくない。この場合断熱性能などは損なわれるため、ガラスパネルを交換しなければならないが、交換までの間雨風をしのぐことは出来る。
割れやすいガラスを割れにくくした強化ガラスがある。普通の板ガラスをその溶融点に近い約700℃に加熱した後急冷することにより、ガラスのすべての表面にあらかじめ圧縮応力を付加し、何らかの理由で発生する引張り応力を緩和することが出来る。このような強化ガラスは同じ厚さの通常のガラスに比べ4倍程度の強度がある。また強化ガラスは割れる際に破片が粒状となり、通常のガラスのような鋭利な端部が発生しないため危険性がない。
強化された窓ガラスでもバットなどで叩けば割れるが、防犯用には2枚のガラスの間にプラスチックのシートをはさみ接着した合せガラスが使用される。ガラスの厚みや中間のプラスチックフィルムの厚みにより高い防犯機能を発揮させることが出来る。なおこのような合せガラスは割れても破片が飛散しないため、自動車や鉄道などのウィンドシールドにも広く使用されている。
なお、網入りガラスは防犯機能があるように見えるが、火災などでガラスが高温にさらされた時、ガラスが割れて脱落することを防ぐために金属製の網が入っているのであり、防犯性能は網のないガラスと大差ない。余談だが網入りガラスの網はガラス切断面では露出しているため、これが水分に触れると錆をおこし、それが原因で割れることがある。これを網入りガラスの錆割れと言う。
建物が破壊するような地震に対しては窓ガラスだけ耐えても意味がないが、窓ガラスの耐震性については板ガラス協会による昭和40年の駿河湾沖地震や昭和53年の宮城県沖地震に関する窓ガラス破損データがある。これによればスチールサッシュのパテ止め固定窓がもっとも危険だと言う。ガラスをサッシュに固定しているために建物の震動が直接伝わりやすいためで、アルミサッシュに柔軟性のあるシリコンシーラントを使用すれば、窓ガラスの耐震性は格段に向上する。
ガラスの中心部温度が周辺部に比較して高いと、中心部の膨張が周辺部に応力となって負荷され、この応力がその部分の強度を越えるとひび割れを生じるが、このようなガラスの破損は熱割れと呼ばれる。熱割れが発生しやすい条件はガラス中心部と周辺部の温度差が大きくなる天候であり、寒い冬の日の夜、寒い冬の日のとても天気の良い日中、とても日差しの強い夏の日中などがこのような条件となる。また室内側にカーテン、ブラインドなどがガラスの近くにあると、中心部と周辺部の温度差をより大きくする傾向があるため、熱割れを起しやすくなる。熱割れを起したガラスでは破壊線(ひび)がガラスの端部では直角になるのが特徴で、破壊線が途中で分岐しない非分岐破壊は熱応力が比較的低い場合であり、破壊線が枝分かれする分岐破壊は熱応力が高い場合に発生する。窓ガラスが割れたとき、破壊線がガラス端部で直角になっていない場合はその原因は熱割れではなく、投石やボールが当るなどの機械的な衝撃によると考えられる。防火用の網入りガラスは切断する際にガラス端部に傷が付くことによって周辺部の強度が低下し、普通のガラスに比較して熱割れを起しやすい。
2009年12月のブログルにロボット兵器のことを書いたが、昨日のNew York Times電子版に軍事用無人機に関する記事が掲載されている。
これまでにロボット兵器を使用したことが知られているのはアメリカ、イギリス、イスラエルだが、現在、軍事用無人機はアメリカだけではなく、中国およびイスラエルが積極的に開発しており、更にロシア、インド、イランなども開発中で、既に50カ国以上が偵察用または攻撃用無人機を所有しているとのことだ。先月23日に打上げられた日本のH2Aロケット19号も北朝鮮のミサイル発射を監視するために開発され、その目的は地上60センチの物体を判別出来る偵察衛星なので、日本もこの50カ国に含まれているのだろう。
オバマ大統領は就任以来、イラクやアフガニスタンでのアメリカ人兵士の死傷者を減らすためにロボット兵器の開発を促進してきたが、アメリカは現在7,000機の偵察用および攻撃用ロボット兵器を所有しており、今ではアメリカ空軍は戦闘機や爆撃機のパイロットの養成よりも無人機のパイロット養成に力を入れている。
先週ボストンの若者が、爆発物を搭載した模型飛行機による連邦議会議事堂の攻撃を計画した罪で逮捕されたことは記憶に新しい。また先月イエメンでアルカイダのナンバー2であるアメリカ国籍のアンワル・アル・アウラキが無人機の攻撃により殺害された。イラクやアフガニスタンでは無人機による攻撃は日常的に行われ、パキスタンでも2,000人以上の敵兵を殺害している。
ラジコンヘリコプター愛好家のくまごろうとしてはリモコン模型が兵器に使用されることは悲しいことだが、所詮戦争とは殺し合い、兵士が発射したミサイルと無人機による殺傷に違いはない。鉄腕アトムの世界のように、ロボットは決して人に刃を向けない世の中になってほしいものだ。
9月4日付ブログルでは、わがやの柚子には2つしか花が咲かなかったと書いたが、実はもうひとつ咲いていた。ただこの花は早くに散ってしまい、くまごろうにはあまり花を楽しませてくれなかった。そのため、この花は実にはならないだろうと諦めていたのだが、9月中頃に柚子の木をよく見ると、もうひとつ実がなっているではないか。他の2つの実と遜色ない大きさですくすくと育っている。
この写真では前回紹介した実と、隠れていたもうひとつの実が写っている。この木にはこの他にもうひとつ実がなっている。実はいずれも直径が20ミリ位になっており、これなら12月頃にはゴルフボール程度に成長するのではないか、と期待している。1ヶ月の間に8ミリ程度成長したことになる。
昨年10月23日付のブログルの写真では黄色くなった大きな実がふたつなっているが、今年はこの大きさまで育つか自信がない。でも今から10年後にこの木がくまごろうよりも高くなり、たくさんの実をつけることを夢見て大切に育ててゆこう。

本日付のNew York Times電子版によれば、North Dakotaでは毎日150万立方フィートを超えるシェールガスがガス井のフレアスタックで燃やされているそうだ。このシェールガスは50万戸の住宅または38万台の中型車をまかなうエネルギーに匹敵し、毎年200万トン以上の二酸化炭素を発生させている。無駄に燃やしているシェールガスはNorth Dakota州におけるシェールガス生産量の30%に相当する。
1990年以来シェールガスは将来の有望エネルギー源として注目され、この資源が豊富なアメリカではシェールガス開発が盛んで、アメリカ中西部だけでも現在5,000基あるガス井が今後20年間に48,000基になると予想されている。
せっかく開発されたシェールガスがなぜ無駄に燃やされているかというと、鉱区のリース期間が5年程度と短いシェールガスフィールドでは、石油価格が高騰している現在、開発業者は同じ油井に存在する石油を生産して販売した方が、長期的な投資であるシェールガスのシカゴなどの大都市に輸送するパイプラインの敷設や、日本などに輸出するための液化プラント建設より安直に利益が得られるからだ。シェールガスの生産には水圧破砕法や水平坑井掘削などの新技術が開発され、これらの新技術が同じ鉱脈からの石油生産を可能にしているのは皮肉なことである。今後シェールガス開発が計画されているTexas、Oklahoma、Arkansas、Ohioなどでもシェールガスが無駄に燃やされる恐れは高い。
アメリカの環境庁はシェールガスの無駄な燃焼を懸念しており、将来はシェールガスの利用を明確にしない限り開発許可を与えないことを検討している。またあるシェールガス開発業者はメタンがほとんどの天然ガスと異なり、シェールガスはプロパンやブタンも含んでいるためこれらを分離してより高価格で販売することにより、採算性を改善出来ると言っている。
日本にとってもっとも重要かつ親密な同盟国であるアメリカからシェールガスを輸入し、コンバインドサイクルのガスタービンによる熱効率50%の発電を行うシステムが構築されることが、原子力発電に不安を感じている日本のエネルギー安全保障にとってもっとも好ましいのではないだろうか。この場合原子力発電よりは二酸化炭素の排出量は増えるが他の化石燃料による発電より少なく、また発電コストの点では再生可能エネルギーよりもはるかに優れている。
先週の9月23日にCERN(European Organization for Nuclear Research)のセミナーで発表されたニュートリノの速度が光速を超えた、というニュースはきわめて衝撃的である。1905年にアインシュタインが発表した特殊相対性理論によれば、質量のある物質は光速(秒速30万km)を超えることが出来ないことになっている。もしも発表されたデータが正しければ特殊相対性理論を否定し、素粒子物理学や宇宙物理学などに大きな変革をもたらすことになる。
David Brownの小説『天使と悪魔』にも登場する、スイスのジュネーブ郊外にあるCERNのLarge Hadron Collider(LHC)を使って陽子を加速してグラファイトに衝突させ、ニュートリノを発生させる。発生したニュートリノビームを730km離れたイタリアのGran Sasso National Laboratoryの地下1400mにある検出器に送り、ニュートリノがミューニュートリノやタウニュートリノに変換することを観測していたところ、ニュートリノが光速より60ナノ秒(ナノは10⁻⁹)早く検出されたという。この観測は主にイタリアと日本を中心とする11カ国の160名の物理学者により3年に渡り行われたが、ニュートリノの速度測定精度に関しては距離はGPSを使用し誤差20cm、時間の計測はGPSからの時刻をセシウム時計で補正し1.4-3.2ナノ秒の誤差とのことである。
CERNはこのデータの精度を注意深く検討してきたが、新事実のデータの公表により見落とされた点がないかを検証してほしい、と世界中の研究者に呼びかけている。特にこれまで茨城県東海村の高エネルギー研究所から岐阜県神岡のスーパーカミオカンデにニュートリノビームを送ってきた実績のある日本に期待を寄せている。
素粒子物理学や宇宙物理学では銀河系やその中の太陽系はもちろん、地球もその上に存在するすべての物質はビッグバンの際の物質と反物質の量のバランスが、わずかばかり物質の方が多かったために生じた、と言っている。すなわちわれわれはすべて星屑によって成り立っているのだ。星屑同士が喜び、悲しみ、愛し、憎みあって生きているこの世の中、ひとりひとりが自身を星屑であることを自覚すればもう少し住みよい平和な世界になるのだろう。
9月初めにアメリカの太陽光発電パネルメーカーSolyndra社が会社更生法を申請したことをブログに記したが、本日付のNew York Times電子版ではこの倒産により、オバマ政権が当惑しているという記事が掲載されている。
オバマ政権は景気浮揚策および雇用対策としてエネルギー開発に対する連邦政府による融資保証プランを発表し、その一環としてエネルギー省が再生可能エネルギー事業に対する融資保証プログラムを推進してきた。このプログラムに対し143社より融資保証の申し込みがあったが、エネルギー省はその中の16社に計画書の提出を求めた。Solyndra社は最終的に太陽光発電パネルメーカーとしては最高の5.35億ドルの融資保証を受けることが出来、カリフォルニアに新工場を建設した。昨年5月には多忙なスケジュールを調整してオバマ大統領が新工場を訪問し、同社の経営者や従業員を前に『Solyndra社のような会社がわれわれのより輝かしい未来をつくるのだ。』という演説までしている。
Solyndra社は2008年以来ワシントンDCでロビイストを使い、連邦政府の融資保証を受けるべく色々と画策してきたらしい。6つのコンサルタント会社に総額180万ドルを払ってホワイトハウス、連邦議会、エネルギー省の要人などに売込みを図ってきたようだ。通常では実現出来ないオバマ大統領の同社訪問はその成果の一つといえる。今になってエネルギー省は融資保証を受ける際に必須の経営内容の審査なども十分に実施しておらず、杜撰な審査だったことが明らかになってきている。
Solyndra社の経営不振は太陽光発電コンポーネントの価格が世界規模で急速に下落したため、との理由付けがなされているが、そのような経営環境でも生き延びている企業もある。来年大統領選挙を迎えるアメリカでは、Solyndra社の会社更生法申請による焦げ付いた多額の政府保証が共和党のオバマ民主党政権批判の新たな材料になるだろう。
このところ毎週、ホームコースの7番ホール左手にあるイタリアンプラムを収穫している。今日の土曜定例ゴルフでも9個収穫した。時間があればもっと収穫出来るが、パー5のセカンドショットの後にこの木に近づいて収穫し、他の人が3打目を打つ前に自分のボールのところに行かなければならないため結構忙しい。ちなみに今日はこのホールではダブルボギーとなった。プラム収穫期にはこのホールでは心がゴルフ以外にも向くため、やむを得ないだろう。
前にも書いたがくまごろう自身はプラムには興味がないため、これはすべて洋子さんのためだ。この木の他にイタリアンプラムの木が2、3本あるので、来週もいくつか収穫出来るだろう。当分の間、このホールでパーやバーディーを出すことは望めないだろう。
- If you are a bloguru member, please login.
Login
- If you are not a bloguru member, you may request a free account here:
Request Account






 kito
kito  shiropoko
shiropoko